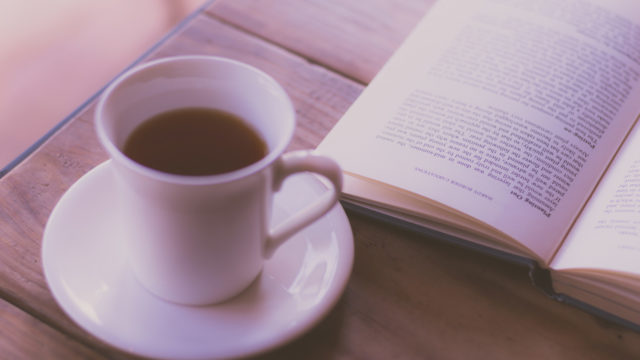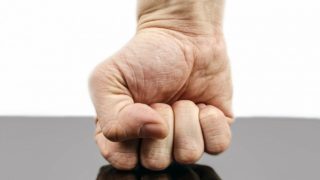「基本的信頼感」という言葉をご存知でしょうか?
これは、アメリカの発達心理学者であるエリク・H・エリクソンが「ライフサイクル論」の中で示した考え方です。
このライフサイクル論は、心理社会発達理論とも呼ばれ、人間の一生を「ライフサイクル」と捉え、精神発達の過程を8つの段階に分けると共に、各段階にある課題を克服することで精神的発達を遂げるとしたものです。
このライフサイクル論によれば、まだ言葉の話せない生まれたばかりから1歳半くらいの乳児期には、基本的信頼感を獲得することが、子育ての大事な目標になると伝えています。
実は、アドラー心理学の教えと、この基本的信頼感には多数の共通点があります。
今回は、基本的信頼感をご紹介したうえで、アドラー心理学との共通点をご説明します。
そして、乳児期のお子さんが基本的信頼感を得るうえで、親がどのように接するべきかについてお伝えしていきます。
目次
基本的信頼感とアドラー心理学との共通点

エリクソンの提唱したライフサイクル論
まず始めに、エリクソンの提唱したライフサイクル論ですが、エリクソンによれば、人間の成長は、8つの段階に分けられると考えられています。
- 乳児期(0-1歳6か月ごろ)
- 幼児期 初期(1歳6か月-4歳ごろ)
- 幼児期(4歳-6歳ごろ)
- 学童期(5歳-12歳ごろ)
- 青年期(12歳-18歳ごろ)
- 成人期 初期(18歳-40歳ごろ)
- 成人期 後期(40歳-65歳ごろ)
- 老年期(65歳以上)
ライフサイクル論では、人生の8つの段階において、プラスの力(発達課題)とマイナスな力(危機)が対になっていて、そのプラスとマイナスとの力の関係性が、人として発達するのに大きく影響すると伝えています。
ここで注目したいのは、プラスの面だけ習得する、マイナスの面だけ習得するということではないとも伝えている点です。
マイナスな力を克服することで、プラスの力にもなり得るし、プラスの力は各段階以降に取得することも可能だと説いています。
基本的信頼感とは?
エリクソンは、基本的信頼を「育ててくれる親への、人格的な信頼感を通し、自分がこの世に存在することを肯定的に捉え、人生には生きる意味や生存する価値があり、世界は信頼するに足るものだという感覚を持つこと」と定義しています。
エリクソンは、この基本的信頼感の獲得を、乳児期における発達課題としています。
生きていて大丈夫だという信頼感や自己肯定感が、自分が本当の自分であるという感覚を養うことに繋がり、それが、他人の信頼や期待に応えようとする姿勢を育てると教えています。
基本的信頼感とアドラー心理学の共通点
このエリクソンの提唱する基本的信頼感と、アドラー心理学の教えには、非常に多くの共通点があります。
「育ててくれる親への人格的な信頼」とは、アドラー心理学で教える「他者信頼」。
「この世に存在することを肯定的に捉え、人生には生きる意味や生存する価値がある」とは、アドラー心理学でいう「自己受容」。
「他人が信頼や期待に応える自分になるという姿勢」とは、アドラー心理学でいう「他者貢献」であったり、「共同体感覚」に他なりません。
つまり、乳児期における基本的信頼感の獲得には、アドラー心理学が教える幸せに生きるヒントを獲得するプロセスと言うことができると思います。
子供が基本的信頼感を獲得するために親ができること

乳児期の子供は、自分で何かをすることができません。
ただただ泣くことで、親に対して自分の意思を示して、自分の課題を解決しようとします。
「お腹が空いた。」
「おむつが汚れて気持ち悪い。」
「眠い。けれども、眠れない。」
こういったとき乳児期の子供はおおきな声をあげて泣き、親の関心を引こうとしますよね。
この時、親が、子供のあるがままの存在を受け入れて、課題に対処してあげれば、子供は「困ってもなんとかなる」「自分は大丈夫だ」という感覚を持つことができる。
機嫌が良い時は、笑っていますが、この時、親も一緒に笑ってあげる。
そうすると、子供は「この世はいいところだ」という感覚を持つことができる。
ありのままの存在を受け入れてあげ、子供の課題に対処してあげることで、子供が基本的信頼感を得らえれるようになるのです。
プラスとマイナスは、6:4くらいのバランスでいい!
では、子供が泣いたら、すべて対応し課題を解決してあげなければならないか?
そんなことはありません。
乳児期の子供のお世話はとにかく疲れるもの。
親が、「子供の欲求のすべてに対応できないこと」に悲観的になり、余裕を無くしてしまっては、子供とのコミュニケーションも少なくなってしまいます。
もう一度、エリクソンの考え方に注目してみましょう。
エリクソンは、「プラスの面だけ習得する、マイナスの面だけ習得するということではない」「マイナスな力を克服することで、プラスの力にもなり得る」と教えていました。
つまり、課題が解決されない状態にいることも、乳児期の子供にとっては大切なことなのです。
このプラスとマイナスとのバランスは6:4くらいで良いとも言われていて、最終的に、乳児期の子供がプラスの面を多く感じられるようになればそれで良いのです。
まとめ
今回の記事では、以下の点についてお伝えしました。
- ライフサイクル論では、基本的信頼感を得ることを乳児期の発達課題としている。
- 基本的信頼感とは、親への信頼感を通し、自分がこの世に存在することを肯定的に捉え、人生の生きる意味・価値を感じ、世界は信頼するに足るものだという感覚を持つこと。
- 基本信頼感とアドラー心理学の教えには多くの共通点があり、基本信頼感の獲得は、アドラー心理学が教える幸せに生きるヒントの獲得につながること。
- 乳児期の子供が基本的信頼感を獲得するには、プラスの面が上回るように子供の課題に対処しておげること。
乳児期のお子さんのお世話はとても大変ですが、この時期を頑張ることで、お子さんが幸せに生きるヒントを掴んでくれたら、こんなに嬉しいことはありませんよね。
ぜひ、このような考え方も念頭におきながら、お子さんと接してみてください。